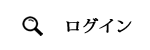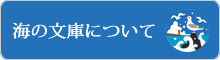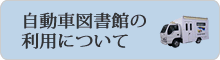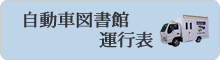呉市立図書館 「読書感想文」
第13回ブックリスト読書感想文 入賞者
呉市立図書館が作成したブックリストの推薦本を対象とした読書感想文募集に,307名の応募がありました。
たくさんの御応募ありがとうございました。
その中から選ばれました入賞者12名を紹介します。おめでとうございます。
小学生の部
最優秀賞 阿 賀 小学校 6年 大 塚 緋奈乃
優秀賞 原 小学校 1年 山 田 日菜子
佳作 呉 中 央 小学校 1年 下 川 瑞 世
広 小学校 3年 寺 口 凰 来
宮 原 小学校 3年 新 井 晴 太
原 小学校 4年 牛 尾 奏音已
中学生の部
最優秀賞 安 浦 中学校 2年 小 林 虎ノ介
優秀賞 白 岳 中学校 2年 稲 垣 ありさ
佳作 白 岳 中学校 1年 グエン ティエン
白 岳 中学校 1年 吉 岡 紗 良
広 中 央 中学校 1年 田 村 恵 理
呉 青 山 中学校 2年 海 生 玲 圭

最優秀賞を受賞されました2名の感想文を紹介します。
- 小学生の部 阿 賀 小学校 6年 大 塚 緋奈乃
- 中学生の部 安 浦 中学校 2年 小 林 虎ノ介
小学生の部「ロドリゴ・ラウバインと従者クニルプス」 阿賀小学校 6年 大塚 緋奈乃

私はブックリストの中にこの本を見つけて心がおどった。私はミヒャエル・エンデの作品が好きだ。特に代表作の「モモ」や「はてしない物語」はその世界に夢中になった。エンデの作品にはいつもみ力的な登場人物が出てくる。この本にも個性豊かなキャラクターが複数登場する。しっかり者の姫、邪悪な魔術師、物語の行方を追って飛びまわるオウム、そして表向きは極悪人に見せかけているが、実は心優しくこわがり屋のロドリゴ・ラウバインと主人公、クニルプス。この物語のテーマは「おそれ」とそれを乗りこえる「勇気」ではないだろうか。クニルプスは初め、善悪の区別がつかず、こわいもの知らず。でもこれは、勇気とは違い知識が無いが故に何も乗りこえる必要がなかっただけである。だが、ロドリゴや姫との出会いの中で、初めておそれを感じる。自分がおかした罪やそれによって大切な人に危険を及ぼしてしまうというおそれ。それと同時に大切な人を守るために力がわいてくることに気づく。この力こそが本当の「勇気」なのだ。「おそれ」と「勇気」は真逆の意味の様にも思えるが、実はおそれがあるからこそそれに立ち向かうための勇気が生まれる。
これは日常生活においても言えることである。私達の生活に邪悪な魔術師や竜は登場しないが、それに代わる悪によって危険な目にあうことがある。それをさけるため内にこもるのではなく必要な知識や経験をもとに正しく「おそれ」をいだき、勇気を持って立ち向かうことが日常を豊かなものにするのではないだろうか。
「おそれ」と「勇気」は表裏一体だと言えるのである。
中学生の部 最優秀賞 「ハーベスト」 安浦中学校 2年 小林 虎ノ介

「ハーベストって何。」
この本のタイトルが気になり調べると、「農作物などの収穫」という意味だった。この物語は、園芸部に所属する三人が、ぶつかり合いながらもお互い理解を深め、成長していく物語だ。
主人公の朔弥は人と話すのが苦手で、担任の先生にすすめられるまま園芸部に入る。個性もバラバラな三人が、学校の花壇に花や野菜を植える部活動を通して、お互いの心の距離を縮めていき、それぞれの「居場所」を見つけていく。
この本の中で、「自意識過剰」という言葉がたびたび出てくる。自意識過剰とは、自分が他の人にどう思われたり、見られたりしているのかを、必要以上に考えてしまうことで、主人公の朔弥が常に思っていることだった。言いたいことをすぐ言えない朔弥の姿に、ぼくは自然と自分の姿を重ねていた。
ぼくは自分の発言に自信がなく、自分の発言で相手がどう思ってしまうかを気にしてしまう、いわゆる「自意識過剰」だということに気づいた。積極的に発表したいわけでもなく、だれかに何か指摘されても、あまり反論するのはすきではない。だから、朔弥に共感できる部分がたくさんあった。でも朔弥は園芸部に入り、少しずつ自分から発言するようになり、自分の思いを伝えることができるようになっていく姿を見て、自分も(このままではいけないな)と思った。
それからのぼくは、自分の意見をしっかり伝えること、授業で積極的に発表することを心がけ実行にうつした。意見が食い違うこともあるけど、相手も自分の思いを理解して付き合うことができるようになったし、間違ってもいいんだと思えるようになったのが大きな「収穫」だった。
世の中には自分の「居場所」がないと思いこんで、生きづらさを感じている人も多くいるようだ。朔弥も自分の居場所がないから、生きる価値がないと思っていた。しかし、お母さんに自分の思いをぶつけることで、初めてお母さんの本心を知り、それが自分が勝手に想像していた思いとは全く異なることに気づくことができた。対話は一方通行では成り立たず、お互いが意見や思いを伝え、歩み寄ることで初めて成立する。どんな人にも居場所があり、それを見つけるためには、家でも学校でも、しっかり対話し、お互いに理解を深めていくことが大切なことだと分かった。
幸せなことに、ぼくには「居場所」がいくつもある。その居場所を居心地のよい場所にするため、これからもしっかり自分の思いを伝え、家族や友人など、ぼくと関わってくれる人たちと対話できる関係性を築いていこうと思う。