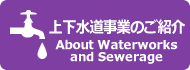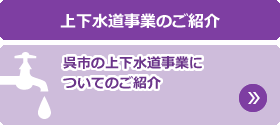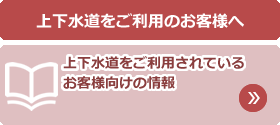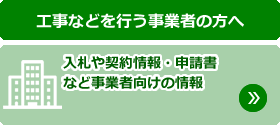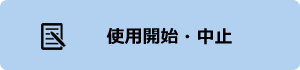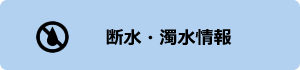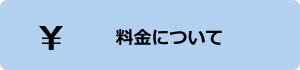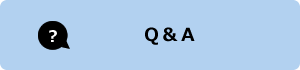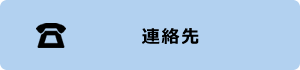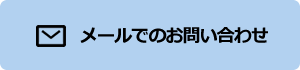呉市上下水道局の文化財を紹介します
呉市の水道は,明治23(1890)年に旧海軍の専用施設である呉鎮守府水道を草分けとして,近代的な水道としては全国で3番目に給水を開始しました。終戦後,国から譲与を受けた水道施設の中には,水道創設期当時のまま現役で稼働しているものもあります。
国指定重要文化財
本庄水源地堰堤水道施設

当時の土木技術の粋を結集して築造した本庄水源地は,堰堤,丸井戸,階段などの関連施設で構成されています。これらは,近代化遺産として歴史的・芸術的な価値が高く評価され,平成11(1999)年に現役の水道施設として全国で初めて国重要文化財に指定されました。
| 概 要 | 貯水量 1,958,500㎥ |
| 完 成 | 大正7年2月 |
| 所 在 地 | 呉市焼山北3丁目 |
| 備 考 | 日本遺産,ダム湖百選 |
国登録有形文化財
三永水源地堰堤

| 概 要 | 貯水量 2,640,000㎥ |
| 完 成 | 昭和18年3月 |
| 所 在 地 | 東広島市西条町下三永 |
| 備 考 | 近代水道百選 |
宮原浄水場低区配水池
明治23(1890)年,呉鎮守府水道の配水池として築造されました。
地下約6mまで掘り下げた位置から石を積み上げた上屋式で,その上屋部分は赤レンガ造りとなっています。平成25(2013)年3月に新しい配水池が完成するまでの123年間,稼働しました。
| 概 要 | 有効貯水量 8,000㎥ |
| 完 成 | 明治23年3月 |
| 所 在 地 | 呉市青山町 |
| 備 考 | 日本遺産,近代水道百選 |
二河水源地取入口

現在は,工業用水の施設として使用しています。
| 概 要 | 石造,延長11.8m |
| 完 成 | 明治22年9月 |
| 所 在 地 | 呉市荘山田村字東二河平 |
| 備 考 | 日本遺産,近代水道百選 |
平原浄水場低区配水池

赤レンガ及びコンクリート造りの半地下式で,通路を中心に左右対称に2つの池が配置されています。南北にある赤レンガ造の換気塔が特徴的で,平成29(2017)年10月に新しい配水池が完成するまでの100年間稼働しました。
| 概 要 | 有効貯水量 6,000㎥ |
| 完 成 | 大正6年12月 |
| 所 在 地 | 呉市平原町 |